2025年4月施行の「流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法改正」とは?
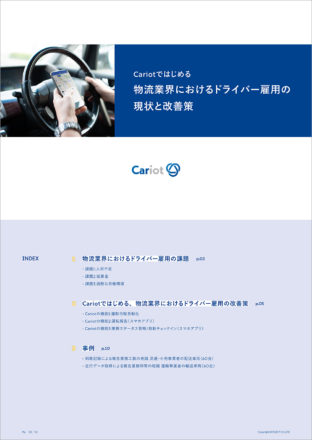
物流業界におけるドライバー雇用の現状と改善策
近年、人材不足や劣悪な労働環境が物流業界全体に悪影響を与えており、特にドライバーの雇用に関する現状は深刻な課題となっています。
本資料では、Cariotのお客さまの実例をもとに、物流業界におけるドライバー雇用の現状を詳細に検証し、要因や問題点を公開します。

こんにちは。Cariot(キャリオット)ブログ編集部です。
2025年4月1日より流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正が施行されます。
この法改正は物流の効率化を促進するために制定され、「物流拠点の適正な配置」や「輸送の効率化」を進めることで、物流コストを削減し、負荷を軽減する目的があります。
この記事では、法改正のポイントや効率化の体制づくりについてご紹介しておりますので、参考にしていただければ幸いです。
1.流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法とは?
2024年4月26日、国会において「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」および「貨物自動車運送事業法」の一部を改正する法律案が可決・成立しました。この改正法(令和6年法律第23号)は、2024年5月15日に公布され、2025年4月1日より施行される予定です。
この改正は、運送事業の効率化や業務の適正化を図るために行われ、「2024年問題」や軽トラック運送業における死亡・重傷事故を減らすために新たに規制を定めるものとなっております。
流通業務総合効率化法
流通業務総合効率化法(物流総合効率化法)は、2005年に施行された法律で正式名称は「流通業の総合化及び効率化の促進に関する法律」です。
ただし、改正法により、今後は「物資の流通の効率化に関する法律(物資流通効率化法)」へと題名が改められます。
この法律は、物流の効率化を促進するために制定され、主な目的は「物流拠点の適正な配置」や「輸送の効率化」を進めることで、物流コストを削減し、負荷を軽減することです。
貨物自動車運送事業法
貨物自動車運送事業法は1989年に施行された法律で、トラック運送業に関するルールを定め、安全・適正な運送サービスの提供を目的としています。
主な内容としては、「事業の許可制度」や「運賃・料金の届出制」「運行管理と安全対策」など、輸送の安全性の向上、貨物自動車運送事業の健全な発達を図ることを目的としています。
法改正までのスケジュール
法改正までに時間がかかるので、今回の物流関連二法は下記のようなスケジュールで法改正が行われます。
- 2024年2月13日 法案の閣議決定
- 2024年3~4月 法案審議(国土交通委員会へ附託)
- 2024年4月~ 働き方改革法の施行(トラックドライバーの時間外労働)
- 2024年4月26日 法案成立
- 2024年5月15日 法律交付
- 2025年4月1日~ 法律の施行①(努力義務・判断基準など)
2026年度~ 法律の施行②(特定事業者の措置など) - 2027年度~ 法令に基づく定期報告の提出開始
参考:「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物⾃動⾞運送事業法の⼀部を改正する法律」の施⾏に向けた検討状況について(国土交通省・経済産業省・農林水産省)
公布日から施行日までには約1年程度設けており、この期間に各事業者は法改正に合わせて準備をする必要があります。
2.なぜ法改正が必要なのか?
今回の法改正の背景にあるのは「2024年問題」です。
2024年問題とは、働き方改革関連法によりトラックドライバーの時間外労働時間が年間960時間に制限されたことに伴って、輸送力不足や物流コスト上昇の問題が起こることを指しています。
そのため、物流の効率化や取引環境の適正化を目的として今回の改正が行われます。
また、運送業による事故数を減らすための安全対策も目的としています。
物流の2024年問題
2024年問題に何も対策を講じないと、今年度中には約14%、2030年度には約34%
の輸送力不足の可能性があり、早急な対応が必要になります。
そのための効率化を目的としていますが、この2024年問題に対しては、物流業者だけでなく、荷主企業や消費者の協力など、総合的な対策によって「商慣行の見直し」や「荷主・消費者の行動変容」も必要になってきます。
参考:物流2024年問題の概要と国土交通省の取組紹介【国土交通省】
運送業における事故の増加
長時間労働や過重労働によるドライバーへの疲労蓄積が、事故増加の要因となっており、事故リスクを減らすためにも、安全対策を強化し、適正な労働環境の整備が急務となっています。
軽トラック運送業における死亡・重傷事故件数は最近6年で倍増したことも指摘されています。
参考:流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律 (国土交通省)
特にECサイト市場の拡大(個人、法人問わず)により、軽トラック運送業の需要が増えたため、事故件数が増加したことも今回の法改正の背景にあります。
3.流通業務総合効率化・貨物自動車運送事業法の改正のポイント
上記のように、ドライバーの労働時間に関する規制が強化されたこと、軽トラック運送業での事故件数が増加したことを受けて法改正が行われますが、実際にどの点が変更になるのか詳しく解説していきましょう。
具体的には下記3つのポイントを意識する必要があります。
- 荷主・物流業者に対する規制
- トラック事業者の取引に関する規制
- 軽トラック事業者に対する規制
荷主・物流事業者に対する規制【流通業務総合効率化法】
荷主・物流業者に対する規制は、荷主(発荷主・着荷主)と物流事業者(トラック、鉄道、港湾・航空輸送、倉庫)に対して物流を効率化させるための規制になります。
努力義務ではありますが、物流効率化のために取り組むべき措置として、国が策定した判断基準に基づいて指導、助言、調査、公表を実施する必要があります。
また、一定規模以上の荷主と物流事業者を「特定事業者」に指定し、中長期計画の作成や定期報告などを義務付けています。
さらに、特定事業者の中でも、荷主及び連鎖化事業者においては、物流統括管理者の選任が義務付けられます。
荷主・物流事業者の判断基準などについて
荷主の判断基準では、流通業務の効率化のために下記のような取り組みが挙げられています。
- 積載率の向上に関して
トラック事業者が複数荷主の貨物の積み合わせ等に積極的に取り組めるよう、適切なリードタイムを確保すること。
また、運航効率向上のため、繁閑期の平準化や納品日の集約等を通じて発送量・納入量を適正化するなど。 - 荷待ち時間の短縮に関して
トラックが集中して到着することがないよう、混雑時間の回避などにより貨物の出荷・納品時間を分散させること。
トラック予約受付システムの導入など。 - 荷役等時間の短縮に関して
パレット等の荷役の効率化に資する輸送用機器を導入すること。
標準仕様パレットを導入すること。
フォークリフトの導入や荷役作業員の適切な配置等により積卸作業の効率化を図るなど。
参考:改正物流効率化法に基づく基本方針、判断基準、指定基準等について(国土交通省)
物流における特定事業者とは?
特定事業者とは以下のいずれかに該当するものを指します。
特定事業者の指定基準での検討では、全体への寄与がより高いと認められる大手の事業者から順に、日本全体の貨物量の半分程度をカバーすることが念頭に置かれています。
- 特定荷主
- 特定連鎖化事業者
- 取扱貨物の重量9万トン以上(上位3,200社程度)
なお、軽い重量の貨物を取り扱う発荷主となる業種や、卸売業、小売業などの着荷主となるケースが多い特殊性を有する業種では、重量の把握に多大なコストがかかることが想定されるため、取扱貨物の重量算定方法は複数の選択肢を提示し、合理的な算定方法を選択する方針です。
- 特定倉庫業者
貨物の保管量70万トン以上(上位70社程度)
倉庫業者が寄託を受けた物品を保管する倉庫において入庫された貨物の年度の合計の重量で算定 - 特定貨物自動車運送事業者等
保有車両台数150台以上(上位790社程度)
保有する事業用自動車の台数で算定
参考:改正物流効率化法の施行に向けた追加論点 (国土交通省)
トラック事業者の取引に対する規制【貨物自動車運送事業法】
今回の法改正で義務付けられたものが、「実運送体制管理簿」の作成、運送契約締結時の書面交付、下請適正化の努力義務・一定規模以上の事業者への義務付けです。
実運送体制管理簿とは?
実運送体制管理簿とは、荷主から運送の委託を受けた元請事業者が、実際に荷物を運んだ実運送事業者の名称などを記載した管理簿で、元請事業者の負担の増加は懸念されますが、物流全体の可視性・透明性の向上が期待されています。
また、下請事業者は次の下請事業者へ実運送体制管理簿作成のための情報の通知をする義務がありますので、この通知義務を忘れないようにしましょう。
ただし、下記に該当する場合は実運送体制管理簿の作成は必要ありません。
- 元請自身が運送を行う場合
- 貨物の重量が1.5トン未満の場合(真荷主から受けた1回の荷物の重量)
- 元請事業者から実運送事業者に至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合
運送契約締結時の書面交付などの義務付け
運送契約を締結する際は、提供する業務の内容や付帯業務量・燃料サーチャージなどの対価もすべて含んだ内容を記載した書面の交付が義務付けられます。
これは運賃値上げや付帯作業の請求の滞りといった業界特有の課題の解決に繋がることが期待されています。
契約締結時に書面に含むものは下記になります。
- 運送の役務の内容及びその対価
- 運送の役務以外で提供される場合は、その内容及び対価
- その他省令で定める事項
下請適正化の努力義務化・一定規模以上の事業者への義務付け
多重下請構造は多くの業界で見られますが、物流業界でも問題になっています。
多重下請の問題点は中間マージンによる実運送会社の収益性の低下や労働条件などの悪化、安全仮体制や責任の所在の問題など多岐に渡り、今回の努力義務化で是正を図っています。
そのため、ほかの事業者へ運送の下請けを行う際は利用の適正化についての努力義務、また、一定の規模以上の事業者に対しては、適正化に関する管理規定の作成や管理者の専任などが義務付けられます。
具体的な努力義務の内容は下記になります。
- 運送に要する費用の概算額を把握し、当該概算額を勘案して利用の申し込みをする
- 荷主が提示する運賃・料金が上記概算額を下回る場合は、荷主に対して、運賃・料金についての交渉をしたい旨を申し出る
- 下請事業者に2段階以上の再委託の制限などの条件を付する
- その他省令で定める措置
軽トラック事業者に対する規制【貨物自動車運送事業法】
軽トラック事業者に対する規制は、ここ数年で増加している事故発生件数を減らすという目的があり、軽トラック事業者は事業の届け出を行った後、速やかに貨物自動車安全管理者を1人選任し、国土交通大臣に届け出る義務が生じます。
また、同管理者を解任した場合も届け出が必要です。
他にも、同管理者には定期講習を受けさせる義務、事故報告が義務付けられます。
今後、軽トラック事業者に係わる事故報告・安全確保命令に関する情報が、国土交通省のウェブサイトに新たに追加される予定です。
また、今回の規制強化の中で「初任運転者等への指導」も義務付けられます。
これは初任運転者として過去に一度も特別な指導を受けていない者、65歳以上の者、事故惹起者を対象に指導を行うというものです。
指導内容は対象によって異なりますが、初任運転者への指導は令和10年3月31日までに実施する必要があります。
また、健康状態の把握や運転者に対して毎年の指導及び監督、点呼なども挙げられます。
詳しくは下記をご覧ください。
参考:貨物軽自動車運送事業における安全規制について(国土交通省)
4.物流関連二法の改正に備えてできる準備
今回の法改正への対策のためには、企業が日々の事業を行いながら、現場や荷主企業の協力を得て対策のステップを進めていく必要があります。
まずは現状の輸配送データを蓄積しそれを可視化すること、次にどこに無駄な時間がかかっているのか?どこに非効率があるのか?の問題を抽出し、そして最後はその問題に対する改善施策を実施するPDCAサイクルを回していく必要があります。
物流効率化のための体制づくり
物流効率化のための体制づくりには、以下の要素が必要です。
各社で取り組むべき施策を検討しましょう。
- 物流事業者や荷主等の連携による物量の平準化
- 荷姿やデータ仕様の標準化推進
- 社内の関係部門(物流・調達・販売等)の連携促進
効率的な輸送システムの導入
- 複合一貫輸送ターミナルの整備
- 基幹的な道路ネットワークの整備
- 共同輸配送やモーダルシフトの推進
時間管理の最適化
- 適切なリードタイムの確保
- 繁閑差の平準化や納品日の集約による発送量・納入量の適正化
- トラック予約受付システムの導入
荷役作業の効率化
- パレット等の荷役効率化に資する輸送用器具の導入
- 検品を効率的に実施するための機器の導入
- フォークリフトの導入や荷役作業員の適切な配置
法的枠組みの活用
- 物流総合効率化法に基づく総合効率化計画の策定と実施
- 特定事業者による中長期計画の作成と定期報告
- 物流統括管理者の選任(特定事業者の荷主)
技術革新と自動化
- 倉庫内での自動化設備の導入による従業員の負担軽減
- 効率的な配送計画やモーダルシフトによるドライバーの負担軽減
柔軟な人員配置
- 変化に対して柔軟かつ効率的に人員を配置できる体制づくり
これらの要素を総合的に考慮し、実施することで、物流効率化のための体制を構築することができます。また、継続的な改善と新技術の導入を行い、将来の物流課題にも対応できる持続可能な体制を整えることが重要です。
業務のシステム化
物流効率化のためには、企業が日々の事業を行いながら、現場や荷主企業の協力を得て対策のステップを進めていく必要があります。
システムを活用して現状の輸配送データを蓄積しそれを可視化すること、次にどこに無駄な時間がかかっているのか?どこに非効率があるのか?の問題を抽出し、そして最後はその問題に対する改善施策を実施する、PDCAサイクルを回していく必要があります。
車両動態管理システムCariotでは、次のようなご支援が可能です。
- リアルタイム車両の位置情報管理と共有
- 危険運転の自動検知とメールアラートによる安全運転管理
- 運転日報のペーパーレス対応
- アルコールチェック結果管理
- 運賃交渉のための運転データの集計と分析
- 車両・ドライバー管理台帳のデジタル化
システムを活用することで、輸配送業務の効率化だけでなく、コスト削減、サービス品質の向上、環境負荷の軽減など、多岐にわたる効果が期待できます。
5.流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法の改正まとめ
2025年4月1日に施行される「流通業務総合効率化法」および「貨物自動車運送事業法」の改正は、物流業界の効率化と安全性向上を目的としています。
特に、2024年問題による輸送力不足の対応や、軽トラック運送業の事故増加への対策が重要なポイントとなります。
今回の改正では、荷主や物流事業者に対する規制強化、トラック事業者の取引適正化、軽トラック事業者の安全対策の義務化などが盛り込まれました。
これにより、物流の効率化が進むとともに、労働環境の適正化や安全対策の強化が期待されます。
施行までの期間を活用し、関係事業者は新たな規制に対応するための準備が求められます。具体的には、物流効率化のための業務改善やシステム導入、安全管理体制の整備などが重要です。
今回の記事を参考に法改正の概要を理解した上で準備、対策を進めるようにしてください。
事前準備が遅れてしまうと、指導の対象になることもあり、業務に影響が出る恐れもありますので、自社での対応が難しい場合は外部の会社を利用することもご検討ください。
弊社では、今回の法改正に対応するためのサポートをさせていただいておりますので、具体的な準備や対策に関してはご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ご意見・ご質問・ご感想・ご要望などがございましたら、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください!
お問い合わせはこちら
※本記事は、一般的な情報を提供することを目的としており、法律的な助言を行うものではありません。また、本記事の内容についての保証はいたしかねます。本記事の利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。

